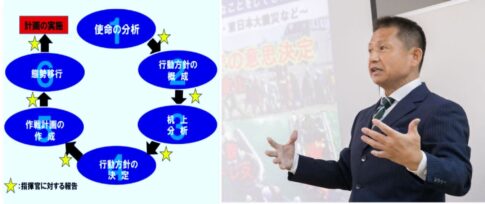2015年12月、オックスフォード大学 カール・ベネディクト・フレイとマイケル・A・オズボーン、野村総合研究所の共同研究結果発表されました。
その発表によると、
「2033年までに日本において会計事務員や配達員などの労働者49%が、人工知能やロボットに置き換えられる可能性が高い」
(2015 年 12 月 2 日 株式会社野村総合研究所ニュースリリースによる)ということなんだそうです。
つまりこの研究結果によれば、14年後現在の労働者が行っている仕事の約半分が、人工 知能やロボットに代替が可能ということになるわけです。
ちなみに人工知能やロボット等による代替可能性が高い職業は(野村総合研究所HPより)
一般事務員 ホテル客室係、CADオペレーターなど、
一方、医師や弁護士、教師、漫画家など創造性やコミュニケーション能力が必要な職業は、代替が難しいことも分かったそうです。(経営者は幸か不幸かそのどちらにも分類されていませんでした。)
これが現実のものとなった場合、49%の仕事を失った人たちは、残り41%に殺到するのでしょうか?
41%の残るほうの仕事はそれなりに難度が高いものが多いので、ある程度年齢がいってからでは、いろいろ難しいでしょうね。
「若い銀行事務員が一念発起して医師になる」、なんてことはなくはないでしょうが、あったらニュースになるくらい珍しいこと。
そう、人間が犬に噛み付いたらニュースになるが、犬が人間に噛み付いてもニュースにはならないのです。
まあ49%はないにしても、30%が失業する世の中を想像してみてください。
よーく考えると30%もの人が失業する世の中で、職のない人を果たして「失業者」と呼ぶのでしょうか?
AI・ロボットに取って代わられる方々はたしかに仕事を失いますが、テクノロジーの発達によって、人類社会全体の生産性は維持されているわけですから、彼らは食べることや寝るところには困らないのだろうと予測されています。
イスラエルの歴史学者ユヴァル・ノア・ハラリはそのベストセラー著書「ホモデウス」で「無用者階級」の出現を唱え、食べることには困らないが、世の中から必要とされない階級が生まれると予言しています。
最初はギョッとしますが、「吸血鬼はなぜ怖いのか?」というお話があります。
ゾンビや中国のキョンシーもそうですが、彼らの怖さの共通点は「噛まれると自分もそうなってしまうこと」
でも、もし世界中のみんなが噛まれてしまって吸血鬼になってしまえば、もう吸血鬼は怖くないのです。
作家の塩野七生によれば古代ローマ帝国では「ローマ市民」はだれでも1日500グラムの小麦を受け取る権利を持っていたそうです(ローマ人の物語Ⅷより)。
現代でいうところの「ベーシックインカム(最低限所得保証制度)」がすでにあったわけですね。
小麦の配給を受けに行くローマ人たちは、基本みんなが持っている権利を行使しているだけですから、そんなに恥ずかしい思いはしなかったのだろうと思うわけです。
古代ローマは、「属州」と呼ばれる半植民地からの小麦の収穫によってこの制度を維持していました。
2033年、現代社会はAI・ロボットによって「仕事をしなくても食うに困らない世の中」を実現する可能性があるということなんじゃないかと、私は思っているわけです。
49%の仕事が失われた分、新しい仕事が生まれるという人もあるが、その仕事は果たして糊口をしのぐためのものではないはずです。
「仕事をするのは食うためじゃない」
そんな世の中になったら企業の役割ってどうなっているのか?
「無用者階級」をAIによって仕事を奪われる労働者階級の事と思ってたら大間違い。
企業経営者が今後も、「自分自身や一族がさらにお金持ちで有り続けること」を目的に 経営し続けるとしたら、、彼らは立派な無用社会級になれるかもしれませんね。
昨今の人材不足は、その予兆のような気がしてならないのです。