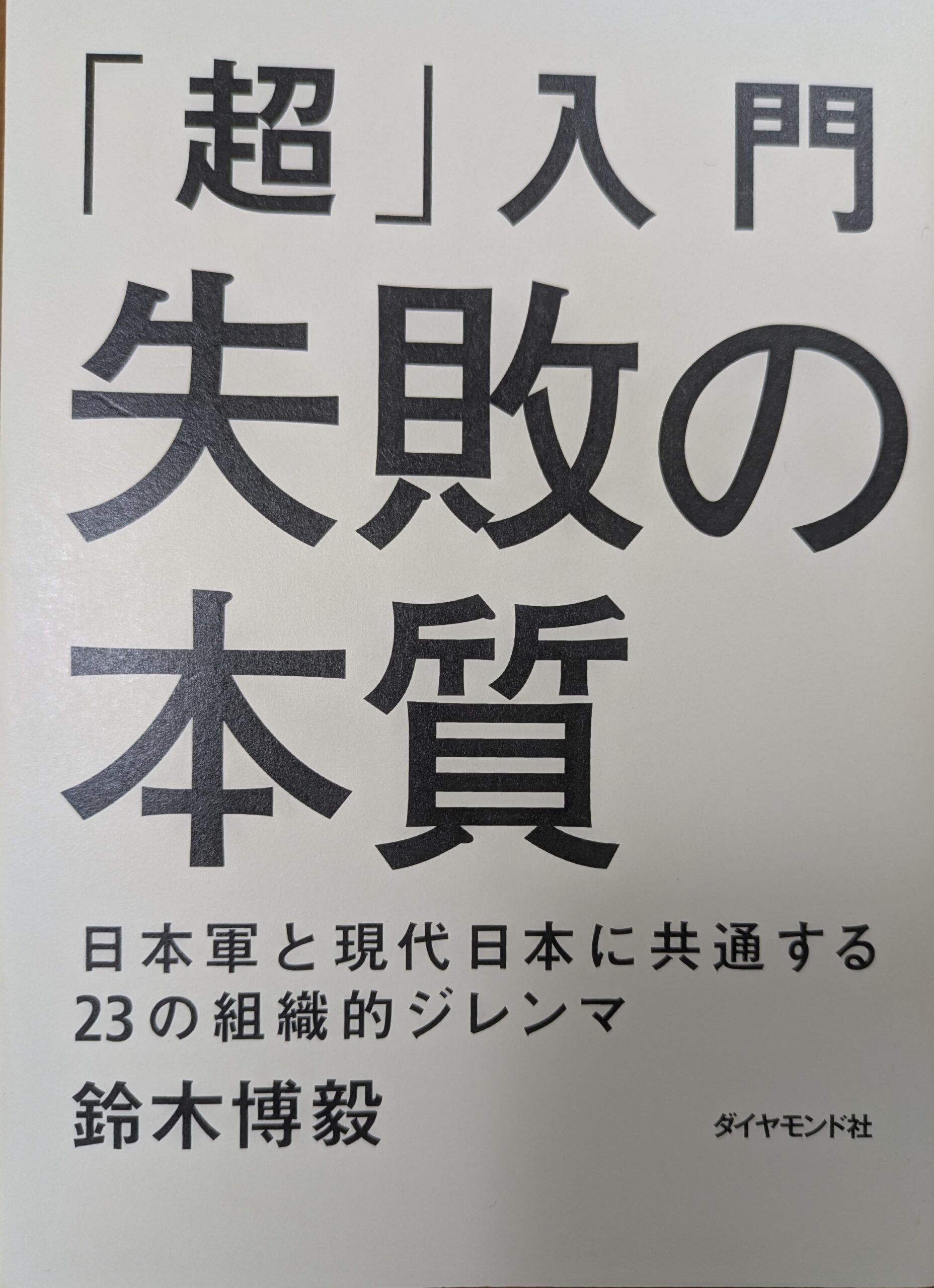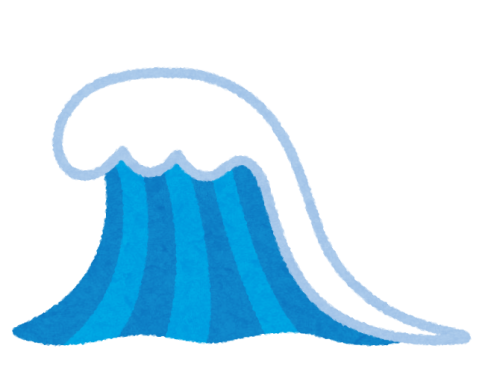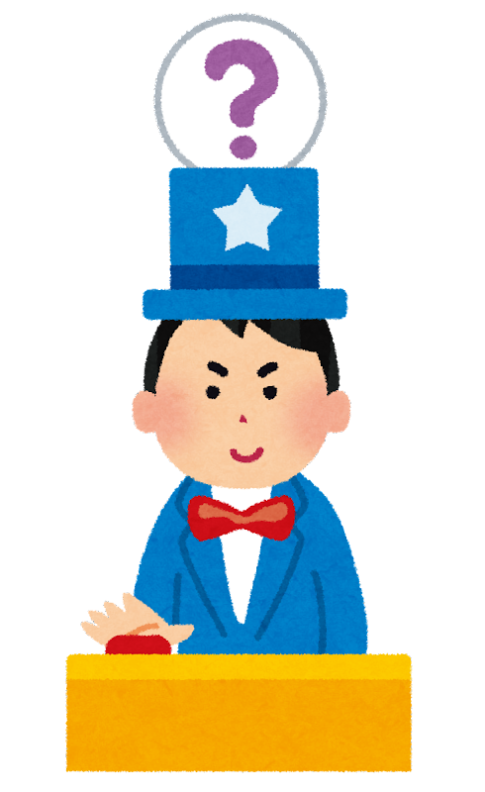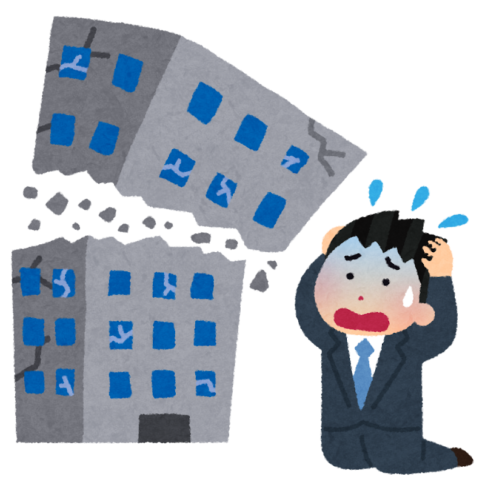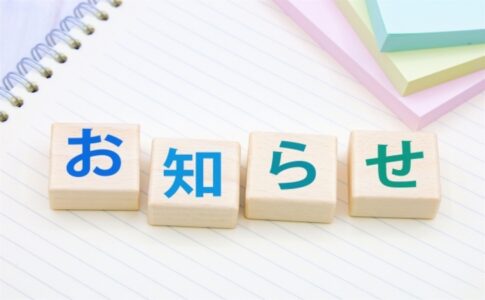どうして私たちは失敗を繰り返すのか
「あーまたやっちゃったよ 途中までいい感じだったのになぁ・・・」
前にもどこかで書いていますが、(特に明治以降の)国際社会における日本って、なんかこういうことの繰り返しのような気がしませんか?
明治〜太平洋戦争の敗戦までの軍拡競争・半導体競争・金融バブルの崩壊などなど、事の善し悪しは別としても、国際舞台の中心に踊り出たとおもえば、競合に負けて失敗。
「いいところまで行って失敗」は、日本という国ばかりでなく私たち中小企業経営者も等しく経験したり、まわりで目にすることではないでしょうか?
名著「失敗の本質」
そんな我々に向けて1984年、名著「失敗の本質~日本軍の組織論的研究」 戸部良一、寺本義也、鎌田伸一、杉之尾孝夫、村井友秀、野中郁次郎・著 (ダイヤモンド社)が上梓されたちまちベストセラーに。
ちなみにこの「本質」シリーズは続編の「戦略の本質リーダーシップ編」や「戦略の本質」「知略の本質」などの著者チームによるもののほかにも「〜の本質」という本が数多く出され、「本質ブーム」ともいえるくらいの盛り上がりを見せました。
難解な「失敗の本質」の「超」入門版が今回の「読んでおこう」
「ユニクロの柳井さんもおすすめ!」というコピーに惹かれ手にとってみた方もいると思いますが、300ページもあるこの本は表現が難解な上に、内容はほぼ戦争のことばかり、何をどうビジネスに活かすかを知るのは一苦労。
そこで今回読んでおきたいのが2012年に出版された、『「超」入門 失敗の本質』です。
読みやすさだけでなく ビジネスへの応用がきちんと解説されています
ページ数は240ページで、本家とそんなに変わりませんが、表現が平易で、わかりやすい図が多く、余白も多め。
いえ、そんなことより著者の鈴木博毅さんは「ガンダムが教えてくれたこと」という組織論の本や、「孫子」や「君主論」などの古典をビジネスに活かす解説本などを書かれている、売れっ子作家にして売れっ子コンサルタント。
しかも本家の著者の一人である野中郁次郎さんからも「本書は日本の組織的問題を読み解く最適な入門書である」という折り紙付きの内容です。
失敗例としての「6つの作戦」
本書では先の大戦における旧日本軍の6つの作戦「ノモンハン事件」「ミッドウェー作戦」「ガダルカナル作戦」「インパール作戦」「レイテ海戦」「沖縄戦」を23のポイントと6つの視点から考え、現代日本の問題と重ね合わせていきます。
現代の失敗例は?
インテル対日本メーカーによる半導体競争敗退、マイクロソフトのOS制覇を許した日本製パソコンの専用システム、世界市場を失った日本家電メーカー、倒産寸前でゴーンに救われた日産などなど、10年以上前の本なので少し事例が古いですが、大戦での失敗と重なり合う部分が多くて気持ち悪いほどです。
「指標の選び方」これが戦略の本質
第1章の「なぜ戦略が曖昧なのか」では「勝利につながる指標をいかに選ぶか」が戦略であると著者はズバッとシンプルに定義しています。
いったん成功すると、条件・環境が変わってもなかなか指標を変えようとしない日本は、アメリカの戦闘機のサッチ・ウィーブ(回旋能力の高い零戦を2機のグラマンで攻撃する)や、夜襲能力に優れる日本陸軍をレーダーや照明弾、更には集音マイクで迎え撃つなど、日本の指標(戦略)を無効にするアメリカのイノベーションに対し、かたくなにこれまでのやり方にこだわった結果、負けを繰り返してしまいます。
日本の家電メーカの失敗 そして中小企業も・・・
これって「性能・品質」にこだわりすぎて高価格になったあげく、中性能低価格の韓国・中国製品による市場の変化があっても指標を変えられず、国際市場を失った日本家電メーカーと重なってきませんか?
大企業ですらそうですから、私たち中小企業もその例に漏れません。
中小企業に多い「体験型学習」
私たちは「やってみて直していく」「やってみて覚える」という体験型学習に上から下まで慣れきっていますし、計画書やマニュアル無しでもそこそこできてしまう能力を「日本人の長所」と考えてしまっています。
「体験型学習」からはイノベーションが生まれにくい
著者は「体験型学習では勝った理由がわからない」を23のポイントの一つに上げています。
日本人は「たまたま」の成功から「たまたま」指標を見つけるから、勝った理由を分析できず、したがってうまく行かなくなっても新しい指標の発見・変更が困難である。
それで日本企業は一回決めた指標に「一点集中」し、大失敗するまで一つの指標で「全面展開」を試み、失敗が明らかになるまでそれをやめないのではないか、とのこと。
「失敗」と骨絡みの私たち
私自身、読めば読むほどこれまでやってきた失敗の数々が、著者があげている23のポイントに引っかかってくることを感じてイヤ〜な汗が出てきます。
かといって、生まれついてからどっぷり浸った日本の風土、何回アク抜きをしても抜けないでしょうし、生まれ変わることもできません。
いったいどうすれいいことやら・・・
「失敗の本質」との向き合い方(著書から導き出された私論です)
「だからわれわれはダメなんだよ」と自虐したり、逆に「相手がひきょう」と責任転嫁しても全く生産性がありません。
私は特に企画部門に人的余裕のない中小企業が競争社会でチャレンジするにあたっては、
「簡単でいいから計画を立てる」→「失敗は当たり前」→「失敗したら隠さない」→「失敗の原因をきちんと分析」→「放置せず対策を打つ」→「必ず実行に移す」→「客観的に観測する」→以下繰り返し。
という、いわゆる高速PDCA的なアプローチが「失敗する運命を持った私たち」には向いているんじゃないかな、と考えています。
そうそう、その作戦行動の「そもそもの目的」の意味を、いつも考え続けることも大切ですね。
目的は途中で考えが深まったり、前提が変わったりすれば修正があって良いと思います。