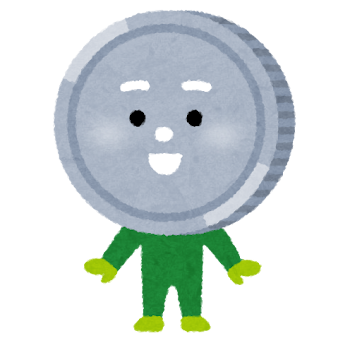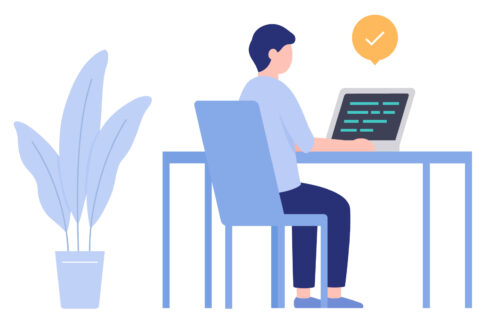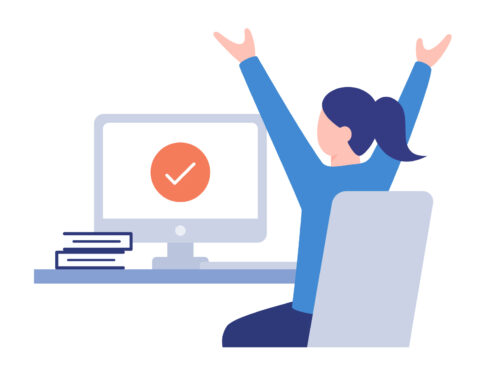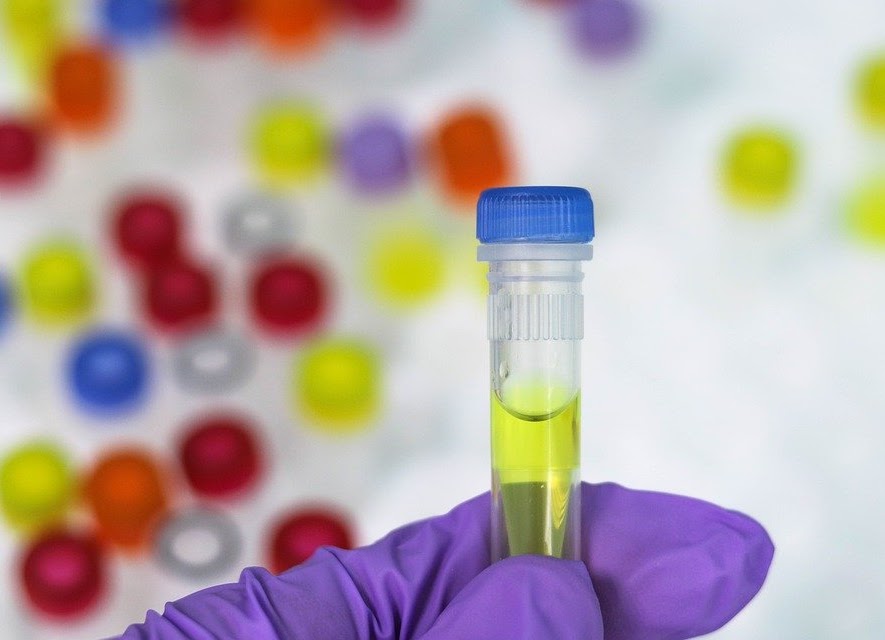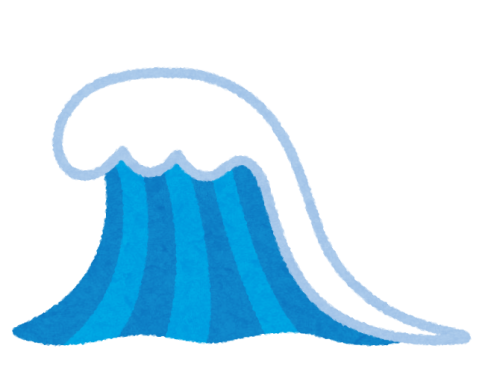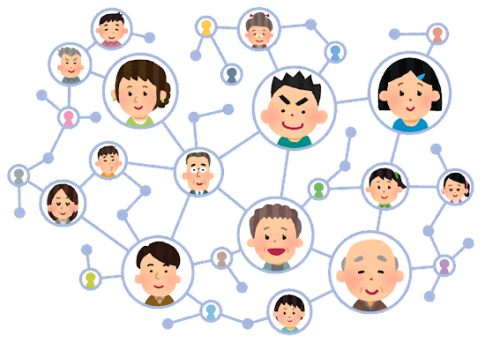前回は自社の経営を通して経営基盤がない世界を体験してきた私がガイド役になり、ビフォアアフター体験ツアー「お金まわり1入金のビフォアアフター」をお届けしました。
今回は前回に引き続き、「経営基盤のある世界」お金まわりビフォアアフター体験ツアーの後編にご案内させていただきます。
私が体験した、経営基盤がもたらすお金まわりの変化、ぜひこのツアーでご確認ください。
ビフォアアフター2 現物と帳簿の不一致
・ビフォア 実際の通帳残高と、帳簿に載っている預金残高が合ってないけど、そのまんまにしている。在庫金額も、現物と帳簿が合ってないまま放置。
当時の総務部長さんは堅物でしたので、現預金の管理はしっかりやってくださっていたはずなのですが、あるとき通帳残高と帳簿上の預金残高のあいだに100万近くの相違が発生、あらぬ疑いをかけられた経理担当が結果的に退職する、という残念な出来事がありました。
どうやら、めったに発生しない外注先への支払いの記帳漏れだったようですが、社員がやめてしまってはもう後の祭り。
責任の所在もウヤムヤのまま、やめた社員の名誉回復もなされず、グレーのままになってしまいました。
また、在庫に関しては、当社はもともと受注生産型ですからロットで仕入をして倉庫から出していくよう在庫がそもそも存在せず、「合わない」ということはないはずなんですが・・・
営業担当が「誤発注」して不良在庫化した部品が、「価値のある」正常在庫としてそのままカウントされていました。
一個一個は高くても10万円前後の部品ですが、チリも積もればなんとやら、いつのまにか数百万単位の不良在庫として残るハメになっていました。
・アフター 実際の通帳残高と、帳簿に載っている預金残高は毎月照合、誤入力は即訂正。不良在庫一掃で現帳一致。
帳簿と通帳の照合は当時6ヶ月に一度しか行ってなかったようで、件の事件の後は毎月締日後にきっちり照合をするようになり、こちらの問題は即解決。
おそらく通帳を持ち歩くリスクを考慮してのことだったのだと思いますが、後味の悪い結果となってしまいました。
在庫の問題は、一個一個がほぼ特注品で、経年劣化して山積みになっているものもあったので、利益の出た年に思い切って一気に除却損を計上、現物も産廃として処理していただき当面の問題は解決。
なぜ誤発注が発生するのか調べてみると、とある営業担当者が定期的な修繕工事に関し、正式な発注がない段階で、部品を先行発注していたことが発覚。
納期を詰めてお客様からほめられたいその一心だったそうで、悪意がないことはわかりましたが、年に数件のハズレくじが積もり積もって数百万のキャッシュロス。
「ちょっとほめられる」程度のためには高すぎる出費です。
販売管理のIT化に合わせて、受注にヒモ付かない製品・部品の仕入れ発注ができないルールに変更して以降、こういった不良在庫は激減しました。
ビフォアアフター3 決算がすぐ出ない
・ビフォア 決算月が終わって結果がわかるまで3か月近くかかり、それまで儲かったのかそうでないのかが分からず、スタートが出遅れる。
当時私は一介の社員でしたが、あの決算月から決算が出るまでのモヤモヤした気持ちを忘れることができません。
ボーナスは出るの?出ないの? 壊れかけの備品は買って良いの?我慢しなきゃいけないの?
12ヶ月の4分の1を、そんなモヤモヤした気持ちで過ごす社員の気持ち、皆さん分かります?
これから書きますように、決算の遅れは経営判断の遅れという戦略的な問題だけではなく、社員士気低下、提供品質の劣化といった戦術的な問題も同時に引き起こしていたんです。
・今期も利益が出るかどうかが分からないので怖くてボーナスを出してあげられない。
2014年のノーベル経済学賞を受賞した、ダロン・アセモグルは著書「国家はなぜ衰退するか」のなかで、衰退の理由の第一に「インセンティブの不足」をあげています。
3ヶ月後、利益が出たことが分かった時には、新しい決算期がもう始まっています。
結局時間切れで、あらたまった期に利益が出るかどうかもわからないので、ボーナスもなんにもなし。
これでやる気が出る! という人がいたら、教えてもらいたいもんです。
・期末に利益が出てるかどうかが分からないので、備品や什器の買い換えをするタイミングがつかめず、どんどん老朽化していく。
どんなに腕の立つ職人やスタッフでも、良い道具がなければ、良い仕事ができません。
当時の私たちは工具・計測具をなかなか新しくすることができず、元請けの管理担当者から「ミカドさん、ホントにそれでやるの?」と聞かれるくらい、古い計測器と工具で仕事をしていました。
正直、精神力だけではどうにもならない世界があります。
精度の落ちた計測器や旧式の工具では当然良い仕事にはなりません。
当時の私たちは、お客様を装備(道具)で失望させ、品質(仕上がり)でも失望させていたわけです。
・アフター 決算月3か月前には落着の予想がついていて、来期に向けた経営判断や行動を起こすことができる。
我がエースグループの中核事業である電気設備工事を主業とするミカド電装商事株式会社では、現在、売上の金額と「注文はいただいたが、まだ納品売上が済んでいない」当期分の受注残の合計だけでなく
見積もり案件の受注確度を4段階に分けて、それぞれの段階別に受注確率を掛けた「見込み」を加えて売上落着の予想をしています。
15年かけて作り上げたこのしくみは、年を追うごとに精度が上がり、現在では決算月の3ヶ月前には±3%の正確さで売上・営業利益の予想が立つようになりました。
そのおかげで、社員の大きなインセンティブになっている期末ボーナス(予測営業利益の30%を出す約束になっています)の見込みが早い段階で立つので、これに合わせて士気も向上します。
また予想利益の一部を前もって、新しい計測具や工具、業務用車の購入費に充てられますので、品質も見た目も向上し「お客様から支持される品質の向上」も可能になりました。
この「お客様から支持される品質の向上」は、現在エースグループの行動指針となっています。
ビフォアアフター4 金融機関に現状と見込みをきちんと説明できない
・ビフォア 取引銀行にこれからの見込みを聞かれてもわからないので、業界の問題点や政策など、他人のせいにしてお茶を濁してしまう。
社長になった最初の年に、赤字を出したものの、その後は「経費削減」の縮小均衡でなんとか黒字っぽく見せていた当社。
とうぜん私が述べる業績不振の理由は、市場構造や競合の価格攻勢、さらには国や自治体の政策の問題にまでその舌鋒がおよぶという、何でも他人のせい、いわゆる「せい病」の状態。
これで、金融機関が積極的にお金を貸そうとするわけはありませんよね。
・アフター 取引銀行にこれからの見込みを聞かれたら、今期はもちろん数年先の見通しや計画はもちろん、ネガティブなリスクまで、よどみなく答えられる。
上記の決算予測の精度が上がったことで、当期の見通しを金融機関にしっかりとお伝えできるようになりました。
現在は当期に起こりえるネガティブなリスクの情報も一切隠しません。
お金を貸している金融機関が一番イヤなことは融資先の成績の見通しが立たないことです。
悪い情報と合わせてその対策もしっかり伝えていくことが、信頼関係を築くことになります。
また考える余裕もできたので、数年先の方針や見通しもしっかり伝えていくことができます。
おかげさまで潤沢になった自前の現金だけでなく、定期的に長期借り入れを起こすことができることで、資金の心配はほぼなくなりました。
経営者の悩みの90%はお金まわり
先月に引き続いての、経営基盤ビフォーアフターお金まわり編、いかがでしたでしょうか?
私はかつて、とある団体の大先輩に「経営者の悩みの90%はお金のことだよ」と教えてもらったことがあります。
経営基盤がお金の悩みを解決
自慢みたいに聞こえてしまったら大変申し訳ありませんが、お金まわりの心配がない経営はとても楽しいものです。
「お金がなくなったらどうしよう?」そんな悩みから、6年間もうつ病の薬を飲むハメになった私も心の底からそう思います。
現在、同じお悩みをお持ちの皆さまが経営基盤のある世界に来ていただき、この90%の悩みから解放されることを願ってやみません。
お金まわりの次に来る課題・・それは「人」の悩み
そして経営者がお金の悩みから解放されると、今度は「人の悩み」が大きくなってきます。
実は経営基盤がしっかりしてくると、人の悩みにも光が差し込んでくるんです。
次回はそんな「経営基盤のある世界:業務・人事編のビフォー・アフター体験ツアー」にご案内いたします、どうぞお楽しみに。